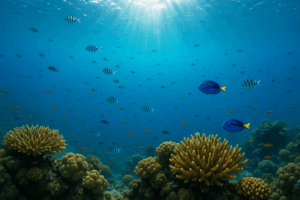目次
日本銀行の株主は、エドモンド・デ・ロスチャイルド。繋がりましたか?
【衝撃】竹中平蔵の闇を潜入捜査した結果…
フェイクニュース撃沈!アラスカ会談を「失敗だ!」と切り捨てたレガシーメディア、まさかの翌日に180度転換
123便墜落直後のテレビ報道実録です。こんなに綺麗な状態での録画は始めて見ました。たぶん、あの日、これをテレビで見てました。 場所はほとんどすぐに特定されていた。横田基地緊急着陸にも言及されていた。
どこが地球環境に優しいのか もう取り返しのつかない状況
消費税導入から35年
日教組の左翼活動家は共生の意味を知らない。
待ってました! 注射接種被害状況のデータベースがついに英訳されました! このデータベースは本当に貴重なものです。
※日航機墜落事故は全て仕組まれていました…命懸けで話すので日本人の皆さんは大至急見て下さい
事故と陰謀説
- 1985年8月12日の日航123便墜落事故は「仕組まれたもの」と主張。
- 機内には「トロンOS」の日本人技術者17名が搭乗。
- アメリカがWindows普及のため、日本の技術を潰す意図で関与したと語る。
- 墜落処理は「自衛隊特殊部隊」によるものとの説を紹介。
戦後日本とアメリカの影響
- GHQ占領政策により「自虐史観」が植え付けられ、日本人は誇りを失った。
- 1985年を「第二の敗戦」の始まりと位置づける。
- 墜落事故の40日後にプラザ合意が締結され、日本経済が弱体化の道へ。
経済・社会政策との関連
- 1985年以降の出来事を「シナリオ」として結びつける:
- 男女雇用機会均等法(社会分断)
- 1989年の消費税導入
- 日米構造協議・バブル崩壊
- 1993年「年次改革要望書」
- 「貿易摩擦」はアメリカが作った政治的造語と説明。
歴史と精神性
- 戦前の日本人は自然や命を尊び、共同体精神で生きていた。
- 英霊や特攻隊員の「母の涙が一番怖い」という言葉を引用し、自己犠牲の精神を強調。
- 現代日本は経済至上主義で、母子分離が進み社会が歪んでいると批判。
結論・呼びかけ
- 1985年からの衰退は「第二の敗戦」であり、日本は意図的に弱体化されてきた。
- しかし日本人には困難を克服してきた歴史がある。
- **「自主独立に向けて立ち上がろう」**と行動を呼びかけて締めくくる。
【衝撃】中国スパイが裏で日本を支配している?このままだと国を乗っ取られるかもしれません…【Noborder /ノーボーダー/溝口勇児】
要約
この動画では、中国による日本へのスパイ活動や経済的侵略について議論されています。主な論点を整理すると以下の通りです。
中国・アメリカの諜報活動
- 日本はアメリカからも監視・盗聴されており、中国からも諜報対象になっている。
- プーチンの発言では「日本は首相官邸だけでなく自宅まで盗聴されている」との指摘もあった。
- 2003年には麻生元首相の携帯が盗聴され、中国大使館が関与していたとの報道も存在。
中国スパイの浸透事例
- 1990年代、中国からの留学生の一部が日本社会に潜入し、民放記者になるケースもあった。
- 上海の軍事学校出身の女性スパイが20年かけて日本社会に溶け込み、民放テレビ局に潜入した事例が紹介される。
- ハニートラップ(性的な誘惑による諜報活動)は政治家や官僚に広く使われ、日本の多くの関係者が引っかかったとされる。
- 実際、鳩山邦夫氏の秘書も中国訪問時に「女性が接触してくるから注意」と警告された経験を語っている。
サイレント・インベージョン(静かな侵略)
- 軍事的侵略ではなく、経済・資本を通じた合法的侵略が進行中。
- 日本は外国資本による買収への規制が世界でも緩く、主要企業(シャープ、NEC、レナウンなど)や不動産が次々と買われている。
- その結果、中国資本が支配権を握るケースが増えており、「静かな侵略」として警戒すべき状況にある。
政治と制度の問題
- 通常の国は安全保障上重要な分野の買収を制限するが、日本は規制が弱い。
- 政府に「相互主義」ルール(相手国が禁止している分野は日本も禁止する)を導入するよう提案されているが、進展していない。
- 野党の一部には規制強化に強く反対する勢力があり、その背後に中国共産党の影響がある可能性も指摘。
結論・警告
- 中国は日本に対し、スパイ活動と経済的支配の両面から影響力を強めている。
- 日本の政治家は規制に消極的で、安全保障意識が欠如している。
- 今後も規制を怠れば、日本の国益や独立性が大きく損なわれる危険があると警鐘を鳴らしている。
【敵は既に内部にいる】国民が無関心のうちにここまで腐敗していた…#noborder #ノーボーダー
要約
この動画では、日本国内の政治・行政・宗教に深く入り込んでいる腐敗や外国勢力の影響について議論されています。主なポイントを整理すると以下の通りです。
政治家と中国マネー
- 政治資金集めの主要手段である「パーティー券」に、中国共産党関係者など外国勢力が参加していた事例が確認されている。
- 外国人による献金は違法だが、パーティー参加費として支払えば合法扱いになり、実態としては政治家に資金が流れている。
- 実際、岸田首相の資金集めにも中国関係者の参加が確認されており、抜け穴を通じて大量資金が流れ込んでいると指摘。
- 投資や企業支援を通じてキックバックが政治家に流れる仕組みも疑われている。
個人情報流出事件と隠蔽
- 500万人分のマイナンバー関連情報が、中国の掲示板に流出した事件が発生。
- 日本年金機構がデータ入力を委託した企業が、契約違反で中国企業に再委託していたことが原因。
- 厚労省が事実を隠蔽したともされ、政府の危機管理意識の低さが批判されている。
政治家の汚職と脆弱性
- 政治家が中国企業からワイロを受け取った事例もあり、表に出た額(100万円程度)以上に大きな金が裏で動いている可能性がある。
- 「日本の政治家は安い金額でも動く」という指摘がなされ、倫理観の低さが問題視された。
- 「放中団」と呼ばれる政治家・企業訪中団でも、歓迎の場で女性によるハニートラップが組織的に仕掛けられていた。
- 多くの政治家が関与した中で、安倍晋三元首相だけが断ったという証言も紹介された。
外務省の関与と内部からの腐敗
- ハニトラの対象者リストなどは、中国側だけでなく、日本の外務省職員からも流れていたとされる。
- つまり「敵は外部だけでなく、内部(日本の官僚組織)にもいる」との見解が示された。
創価学会の影響
- 動画後半では、創価学会の政治的影響について言及。
- 1972年の日中国交正常化で裏で強い影響を及ぼしたとされる。
- 資金力が組織拡大の源泉となり、特に高額な献金・金融活動による資金調達が問題視される。
- 役職者が献金を拒否することは許されない体制だと批判された。
結論・警鐘
- 日本の政治は「中国マネー」「外務省の腐敗」「宗教団体の資金力」によって大きく侵食されている。
- 国民が無関心であることが腐敗を助長しており、選挙に行かないこと自体が「罪」だと強調。
- 国の独立性を守るため、国民が政治腐敗に目を向け、行動する必要があると呼びかけている。
【安野貴博】デジタル大臣が適任すぎる・・AI法案に対する質疑応答【政治・国会】
要約
この動画では、安野貴博議員が AI推進法案 に関する質疑応答で述べた考え方が紹介されています。AIの認知戦リスクや教育、政治活用など幅広い論点が取り上げられています。
AIと認知戦(情報戦)のリスク
- 中国製AIが尖閣諸島を「中国領」と答えるなど、学習データの偏りによる 世論操作や歴史戦への利用 が懸念される。
- 対策は 国産LLMの育成 と、AI技術による防御。
- 人力での対応は限界があるため、技術的な対抗手段が必要。
教育と人材育成
- 2030年には 79万人のIT人材不足 が予測される。
- 解決策は AIへの広いアクセスの確保。
- 例:中高生はChatGPTを活用して学びのスピードが格段に速い。
- 逆に、アクセスを与えられない学生は大きく遅れを取っている。
- 教育格差を防ぐために「平等なAIアクセス」が不可欠。
AI活用の理念
- 人間の可能性を広げる方向にAIを使うこと が重要。
- AIは人間の自由を制限する道具にもなりうるため、理念面の指針が必要。
日本にAI勝機がある理由
- 新技術普及のタイミングでは 既存の勝者が入れ替わる好機 がある。
- 日本は労働人口減少という課題を抱え、AI導入インセンティブが大きい。
- 基盤モデルの競争は難しいが、それを応用した産業活用では無数のチャンスがある。
プロンプトエンジニアリング
- 細かいテクニックは存在するが、将来的にはAIが最適化するため一般利用者は深く知らなくてもよくなる。
- 本質的には「部下をマネジメントするように、適切な情報を与える力」が重要。
若手人材活用
- GoogleやOpenAIなどは 20代前半の若手が主力。
- 日本は理系学生の能力が高いのに、産業で活かせず埋もれている。
- 20代を積極的に産業界で活用できる仕組みが必要。
政治におけるAI活用
- AIは「フェイクニュース拡散」などのリスクと同時に、「多様な声を拾う」可能性も持つ。
- 安野氏は選挙で 自分のマニフェストを学習したAI を用意し、有権者が24時間質問できる仕組みを導入。
- → 有権者の批判やニーズを把握する学びが得られた。
- AIは一方的な「ブロードキャスト」ではなく「ブロードリスニング」を可能にする。
偽情報・ディープフェイク対策
- SNS上の情報拡散スピードに司法処理が追いつかない。
- 技術的対策として「プリバンキング(事前警告型教育)」が有効。
- 例:選挙前に「ディープフェイク映像が出る可能性がある」と周知。
政治家のAIリテラシー
- AIは意思決定の補助ツールとして活用できる。
- ただし、日本の政治家の デジタルリテラシーは不足 しており、向上が必要。
結論
- AI推進法(2024年5月成立) は「人の可能性を広げるAI活用」を理念に掲げた日本初の法律。
- ただし、教育格差や偽情報対策、政治利用のルール整備は今後の課題。
- 日本にはまだ勝機があり、特に若手人材の活用が鍵になると強調された。