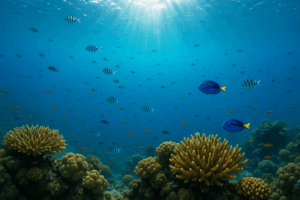目次
トランプ大統領がハッキリ言い切りました。「停戦は必要ない!あくまでも“終戦”だ!」と
媚中な橋下徹氏にはっきり言う櫻井よしこ氏
打とうと思うなら先ず見て下さい!
日本の米不足の発端はこれ
スパイ防止法の制定に関して、 北村弁護士が秋までには確実に法案を出せると断言
ソーラーパネルは環境破壊以外の何物でもない。
トランプ「私はウクライナの人々を愛していますが、すべての人が大好きです。ロシアの人々も愛しています。みんな大好きです。戦争を止めたいです。
日本の裁判官は中国人
日本は中国になる!中国移民の恐るべき脅威|2025年3月15日開催ASAKUKRA経済セミナー「本格化するインフレと中国移民の脅威」ハイライト
要約:ASAKURA経済セミナー「本格化するインフレと中国移民の脅威」(2025年3月15日)
日本は「中国になる」可能性
- 朝倉氏が友人から「日本は中国になる」と警告を受け、現場感覚・データを調べて危機感を抱いた。
- 中国移民は単純労働者だけでなく、資産家やエリート層が大量に流入している。
- 日本社会の中で水面下の大きな変化が起きている。
移民の規模と流入の質
- 世界では移民問題が社会不安の要因となっているが、日本は海と日本語の壁により2%程度に留まっていた。
- しかし、2024年時点で中国人移民は100万人を突破。近年の増加スピードは急激。
- 移民の中心は「頭脳・資産・教育志向を持つ層」であり、旧来の単純労働移民とは質が異なる。
中国からの脱出(ルンリー)
- 習近平政権下のロックダウンや経済失速から逃れるため、多くの富裕層・知識層が日本を選択。
- 日本は近く安全で、教育環境も良いことから「避難先」として人気。
- 彼らは目立たず政治発言を避けるが、教育・不動産を通じて社会に浸透している。
教育現場での影響
- 中国人家庭は全員が中学受験を志向し、サピックスなどの進学塾上位クラスを席巻。
- 東大入学者の10%以上が中国人留学生。
- 文京区・中央区など東大進学を意識した地域に中国人居住が集中し、教育現場は大きく変化。
- 日本人家庭では教育負担による「家庭崩壊」例も報告。
不動産と生活圏
- 豊洲や晴海などの高級マンションでは中国人比率が20%、川口団地では60%に達する。
- 上海の不動産を売却すれば日本のマンションが複数購入できるほど価格差があり、買収が加速。
- 東京だけでなく、温泉街やリゾート地(熱海、伊沢温泉、ニセコ、富良野など)も中国資本に買収されている。
政策と制度の影響
- 日本政府は「高度外国人材」に対し永住権取得条件を5年から1年に短縮。
- 特にアニメ・ゲーム・美術分野の人材が優遇され、美大への中国人留学生が急増。
- 相続税のある日本人と異なり、中国人は資産を世代間で保持できるため、長期的に不動産を保有可能。
結論
- 中国から逃れてきたのは「貧困層」ではなく「エリート層」。
- 教育・不動産・観光地などあらゆる分野で日本社会に浸透しており、将来的にエリート層を占める可能性が高い。
- 日本が「中国になる」という懸念は誇張ではなく、現場レベルで進行中の現実だと警鐘を鳴らしている。
【安野貴博】デジタル大臣が適任すぎる・・AI法案に対する質疑応答【政治・国会】
要約:安野貴博「AI法案に対する質疑応答」
認知戦とAIのリスク
- AIは認知戦に利用されやすく、バイアスによる情報操作の危険性がある。
- 防御には人力ではなく技術的対抗が必要。
- 解決策として「国産LLMの開発」と「技術による認知戦対策」を提示。
国産LLMの開発とは
良いテーマですね。
「国産LLMの開発」とは、ざっくり言えば 日本国内で大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)を自前で開発・運用する取り組み のことです。
1. なぜ国産LLMが必要か
- 言語特性の違い
英語中心のLLMは日本語の文脈・敬語・表記揺れに弱い。日本語に最適化されたモデルが望まれる。 - データ主権
海外企業のAIに依存すると、セキュリティや情報流出のリスクがある。国内独自の基盤を持つことは安全保障の観点でも重要。 - 産業応用
行政文書、医療、日本の法律・金融システムなど、日本固有の知識分野を強化できる。
2. 日本での主な開発プロジェクト
🔹 大学・研究機関
- 理化学研究所(RIKEN)/東京大学
スーパーコンピュータ「富岳」を使ってLLMを学習。 - 産総研(AIST)
日本語コーパスを整備し、オープンモデルを提供。
🔹 民間企業
- NTT
「tsuzumi(つづみ)」という国産LLMを発表。マイクロソフトAzureとも連携。 - ソフトバンク
国内データセンターで学習したLLMをAPI提供。 - PFN(Preferred Networks)
科学・医療分野に特化したモデルを開発。
🔹 オープンソース
- rinna(りんな)
MS発の日本法人から独立、オープンモデルを配布。 - ELYZA(エライザ)
東京大学発スタートアップ。日本語特化モデルを公開。 - CyberAgent AI Lab
Amebaデータを活かした会話・広告系モデルを研究。
3. 課題
- 学習データの不足
高品質な日本語データが少ない。ネット掲示板やSNSは雑多でクレンジングが難しい。 - 計算資源
GPT-4規模を目指すには数千億円規模の計算資源が必要。富岳や商用GPUクラスタを使うがコストが高い。 - 人材不足
データサイエンティスト、AI研究者の層が海外に比べて薄い。
4. 展望
- 政府が「生成AI開発・利用に関する戦略」を打ち出しており、国産LLMを基盤技術として位置付けている。
- 欧米モデルに完全に競合するのではなく、「日本語・日本文化に強い特化型」+「中小規模で軽量」 という路線が有力。
- 教育、医療、法務、行政文書など「国産ならではの強み分野」で普及が進む可能性大。
👉 まとめると
国産LLM開発は「英語中心の海外モデルに依存せず、日本語・日本社会に最適化されたAIを育てる試み」であり、政府・企業・大学が連携して動いています。ただし、規模や資金の面では海外に劣るため、「特化・軽量・安全」 をキーワードに発展していくと見られます。
教育と人材不足への対応
- 2030年に約79万人のIT人材不足が予測。
- 必要なのは「AIへの広いアクセスの保障」。
- 例:ChatGPTを使える学生と使えない学生で格差が拡大。
- 平等なアクセス環境づくりが重要。
AI推進の理念
- 人間の可能性を狭めるのではなく「広げる方向」でAIを活用すべき。
- 日本にも「AIで勝てるチャンスはある」とし、その理由は2点:
- 技術パラダイム転換期には勝者交代が起こりやすい。
- 労働人口減少によりAI導入のインセンティブが強い。
プロンプト活用と将来像
- プロンプトエンジニアリングに多くのテクニックが存在。
- 「深呼吸をしろ」と指示すると精度が上がる例を紹介。
- 将来的には利用者が細かい技術を知らなくても高精度利用が可能に。
- 人材マネジメントのように「適切な情報を与える力」が重要になる。
若手人材の活用
- 海外の基盤モデル企業では20代前半が主力。
- 日本の18歳時点の理系能力は高いが、産業界で活かしきれていない。
- 若い才能を伸ばす仕組みが必要。
政治とAI
- AIは「声を拾う」方向に使える一方、フェイク拡散の危険もある。
- 選挙では「ブロードリスニング」を実施:
- 有権者がAIに24時間質問可能。
- 双方向で批判や意見を把握できた。
- 政治におけるAIの利点:より多くの声を吸い上げ政策改善に役立つ。
偽情報対策
- 課題:SNS上の偽情報の拡散速度に司法処理が追いつかない。
- 技術的対応例:
- 司法処理スピードの向上
- プリバンキング(拡散前に「こういう偽情報が出る可能性」を周知)
政治業界でのAI活用
- AIは意思決定そのものではなく「過去事例や科学的根拠の提示」に有効。
- 政治家のデジタルリテラシー向上が今後の課題。
結論
- AI推進法は「人間の可能性を広げる理念」に立脚して成立。
- ただし「教育格差」「政治利用のルール」「偽情報対策」は未解決課題。
- 日本にとってAIは人材不足解消・国際競争力確保の大きなチャンス。
経済崩壊より深刻な危機──14億828万人はどこへ消えた?北京・上海はゴーストタウン化・昼の地下鉄は空席地獄・ショッピングモールは完全沈黙 |中国を読み解
要約:経済崩壊より深刻な危機──「14億人はどこへ消えた?」
都市・農村に広がる「ゴーストタウン化」
- 中国政府は依然として「人口14億828万人」と公表しているが、実態は空虚。
- 北京・上海・広州・深圳などの大都市でも通りや地下鉄が閑散。
- ショッピングモール、飲食店、商業施設も閉鎖・空室が目立つ。
- 農村部では若者流出と高齢化により無人化が進み、廃墟と化した村が全国的に拡大。
経済失速と消費崩壊
- 米中貿易戦争、債務危機、不動産バブル崩壊、高失業率が重なり経済は急減速。
- 所得減少と節約志向で消費活動がほぼ停止。
- ショッピングモールや市場は閑散とし、昼間に人影が消える異常な現象が広がっている。
人口統計への不信
- 公式発表と体感が大きく乖離。
- 上海公安局データ流出(2022年)では「実人口は約9億7000万人」と記録。
- 専門家の推計でも8〜9億台とされ、公式発表より数億人少ない可能性。
- 住民は葬儀の増加・出生や結婚の減少を目の当たりにし、人口減少を直感している。
パンデミック後の「不可解な消失」
- コロナ以降、死亡者数の統計は非公開化。火葬場の混雑後、突如として沈黙が訪れる。
- 健康な若者が突然亡くなる事例も増加。
- 2023年以降「人々が姿を消す」現象がSNS上で話題化。
生活圏の異変
- 通販やライブ配信に置き換わったとされるが、配達員や視聴者数も激減。
- 高速道路や観光地も空き、人の気配が消えている。
- 上海でも人口減少が体感的に語られている。
最大の疑問
- 経済崩壊以上に深刻なのは「実際の人口がどれほど減少しているのか」という謎。
- 「中国に本当に14億人は存在するのか?」という問いに誰も答えられない。
- SNS上では「人はどこへ消えたのか?」というフレーズが拡散し、静かな警告となっている。
【ウクライナ戦争】プーチン×トランプ首脳会談と今後の行方
プーチン×トランプ首脳会談と今後の行方(要約)
会談の背景と位置づけ
- プーチンとトランプの首脳会談は、表向き「合意なし」と報じられたが、実際は経済・エネルギー・宇宙開発分野で前向きな協力が進んでいる。
- ウクライナ戦争の停戦合意は未決着だが、方向性はすでに固まりつつある。
- この会談は「失敗」ではなく、世界秩序が変わる転換点と位置づけられる。
アメリカの戦略とブリックス
- トランプの基本路線は「経済重視・アメリカ国益優先」。
- 欧州G7よりも、人口大国・資源大国のブリックスやアラブ諸国を重視。
- 「アメリカが拡大ブリックスを支配する日」が構想されている。
- サウジアラビアが仲介役となり、米露サウジの3国協力体制が浮上。
ウクライナ停戦シナリオ
- ロシアの要求:
- ドネツク・ルガンスクをロシアへ
- ウクライナ武装解除
- NATO加盟放棄
- 政権交代(選挙による)
- ゼレンスキーの本音:身の安全・巨額資金・亡命先(UAEドバイが有力)。
- すでに「ゼレンスキー引退と亡命」のシナリオが水面下で調整されている。
- 秋頃〜年内に停戦合意が具体化する見通し。
ヨーロッパの動揺
- フランス・ドイツ・イギリスは経済疲弊で対露妥協に傾きつつある。
- しかしEUやNATOの指導層は戦争継続を志向。
- トランプ政権下では「NATO解体」の可能性も示唆されており、同盟の存続意義が揺らいでいる。
ブリックス拡大の動き
- インド外相ジャイシャンカルが8月21日にロシア訪問予定。
- プーチンも9月中旬にインド訪問の可能性。
- 中国・インド・ロシアの動きと合わせ、拡大ブリックス(エジプト、UAE、イランなど)の結束が強まっている。
- 今回の会談は「ブリックスに追い風」となった。
日本への示唆
- 世界は「米露接近 × ブリックス拡大」へとシフト。
- 日本は未だ対応が遅れ、EU・G7寄りの立場から抜け出せていない。
- 今後、どちらの陣営につくかが問われる。
👉 結論
プーチン×トランプ会談は、表向き「成果なし」と報じられたが、実際には 米露接近・ウクライナ停戦シナリオ・ブリックス拡大 が動き出す大きな転換点となった。世界秩序は秋以降に急速に再編される可能性が高い。
【大西つねき氏 豈プロジェクト特別講演】経営者が絶対に知るべき、財政金融の真実。
大西つねき氏講演「経営者が絶対に知るべき財政金融の真実」要約
お金の本質は「借金」
- 現代のお金は、誰かの「借金」が銀行を通じて預金通帳に数字として記帳されることで生まれる。
- 預金は実際の紙幣ではなく「借金の裏返し」。
- 借金が返済されると、その分お金は消える仕組みになっている。
- よって、借金は常に誰かがし続けないと経済は回らない。
経済成長と金融システム
- お金と借金は増え続ける仕組みのため、「経済成長」が必須条件になる。
- しかし人口減少・消費停滞の中では民間の借金が増えにくくなる。
- 日本では1990年代以降、民間の借金が頭打ちになり、代わりに政府の借金が急増してお金を支えてきた。
政府の赤字=国民の黒字
- 政府支出が税収を超えて赤字になると、国民の所得は増える。
- 逆に政府が黒字(増税・緊縮)になれば、国民はその分貧しくなる。
- 「政府は常に赤字であるべき」というのが現行システムの前提。
日本とアメリカの違い
- アメリカはコロナ禍で巨額の財政支出(4兆ドル)を実施し、ドル高を維持。
- 日本は限定的な支出にとどまり、円安を招いた。
- 背景には「金利差」と国際投資の仕組みがあり、日本人の資産が海外流出している。
MMT(現代貨幣理論)と大西氏の立場
- MMTは「政府は無制限に借金しても破綻しない」と説明する。
- 大西氏はこれに懐疑的で、「借金を続ける限り利息負担が膨らみ、金融機関(特に外国人株主)が利益を得る構造」が問題と指摘。
- 解決策は「政府が誰の借金でもない通貨を直接発行すること(政府通貨)」。
中小企業への提言
- 中小企業の多くが利益を内部留保してお金を滞留させている。
- 本来はお金を循環させることが重要であり、「黒字至上主義」をやめれば経済はもっと回る。
- 中小企業が意識を変えることで、日本全体の資本主義の在り方を変える可能性がある。
結論と活動方針
- 借金を悪とみなす発想こそが問題の根源。
- 政府の借金は国民の資産であり、むしろ積極的に拡大させるべき。
- 将来的には政府通貨発行によって金融機関依存を断ち切る必要がある。
- 大西氏は来年の参院選出馬を予定し、この財政金融の認識を広める活動を展開していく。
👉 要点を一言で言えば:
「借金=悪」という常識を捨て、政府が積極的に赤字を出すことで国民が豊かになる。最終的には政府通貨発行による根本的な制度転換が必要」 という主張です。
トランプ-ゼレンスキー会談 プラス欧州リーダーとの会議【及川幸久】
1. 背景:ベロ会談(トランプ=プーチン)
- 8月15日、アラスカでトランプとプーチンが会談。
- 表向きは「成果なし」と報道されたが、裏では重要な合意。
- プーチンが初めて ウクライナの安全保障スキームを受け入れた とされる。
- つまり「再侵攻しない保証」を認めた。
- ただしその保証の形は未確定。
- NATO軍の駐留ではなく、アメリカ・欧州による特別な集団安全保障スキーム。
- NATO憲章第5条(集団防衛条項)に似た仕組みをウクライナに適用。
2. トランプの新方針
- 以前は「停戦(シースファイア)」を強調 → 今回は「和兵=戦争集結」へ大転換。
- ロシアの勝利を事実上認め、ウクライナに領土譲歩を迫る姿勢。
- 条件
- アメリカは無制限に資金提供しない。
- 主にヨーロッパが費用負担。
- アメリカは安全保障を提供するが軍事介入は限定的。
3. 領土問題
- クリミア → 完全に諦めろというのがトランプの立場。
- ドネツク・ルガンスク → ウクライナ軍は撤退、完全にロシアへ。
- ザポリージャ・ヘルソン → 現在の前線で凍結(現状維持)。
- ホワイトハウスでは「クリミアと東部4州を別色に塗った地図」をゼレンスキーに提示。象徴的な“譲歩要求”。
4. 会議の構図
- 出席者:トランプ、ゼレンスキー、フランス(マクロン)、ドイツ(メルツ首相)、イギリス、イタリア(メローニ)、フィンランド、EUトップ、NATOトップ。
- 欧州側は「停戦」を求める声が根強いが、トランプは「戦争集結」へ。
- ドイツのメルツ首相は「まず停戦が必要」と発言し、場を凍らせる。
- 一方、フィンランド大統領は「過去2週間で過去3年半よりも進展があった」と評価、注目を集める。
5. プーチンへの直接連絡
- トランプは会議中に一度退席し、執務室からプーチンに電話。
- その場に欧州首脳やゼレンスキーは同席させず。
- 電話の結果:
- プーチン=ゼレンスキー直接会談を受け入れ
- その後に トランプを交えた三者会談 を行う流れを確認。
6. 展望
- 三者会談で「和兵=平和協定」がまとまれば戦争終結の可能性が現実味。
- ただし、ゼレンスキーは「憲法で領土譲渡は不可能」と発言しており、国内政治的な難しさが残る。
- しかし現実にはロシアが占拠しているため、「憲法論」は国際的には通用しにくい。
まとめ
この会談のポイントは:
- トランプが「停戦」ではなく「戦争終結」に舵を切った
- プーチンが初めてウクライナへの安全保障を受け入れた
- 領土問題はクリミア放棄+東部4州譲渡で整理されつつある
- 近くプーチン=ゼレンスキー直接会談 → 三者会談 → 和平合意 というシナリオが具体化している。
👉 要するに、この一連の動きは「ウクライナ戦争の出口」が一気に開きつつある歴史的転換点といえる、という見立てでした